【初心者向け】活性汚泥バルキングって何?
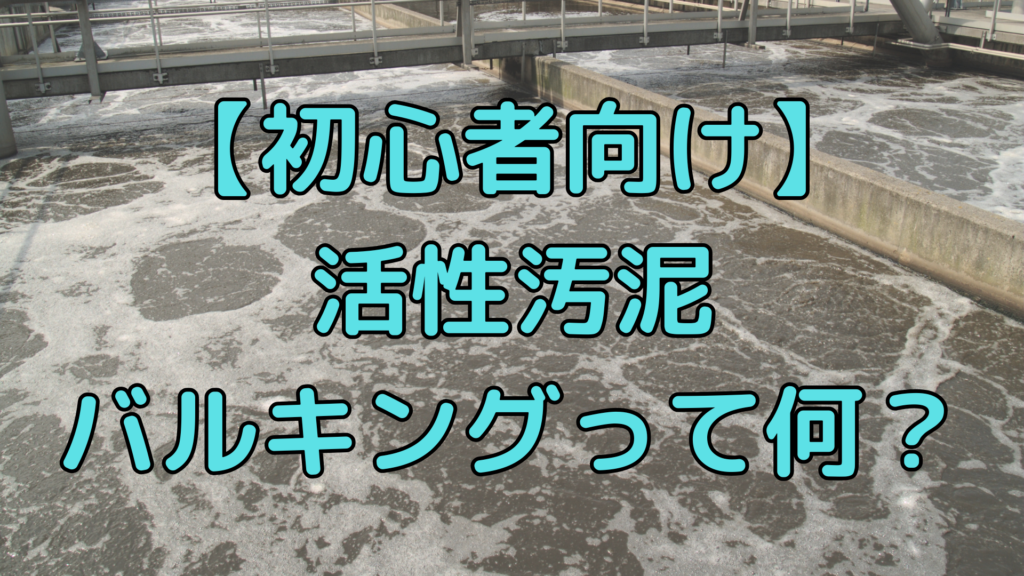
排水処理の現場では、時々「バルキング」という現象が起こることがあります。「バルキング」という言葉、初めて聞いた方もいるかもしれませんね。
今回は、排水処理の基本である活性汚泥法で起こるバルキングについて、その原因と対策を分かりやすく解説します。
活性汚泥って何?
排水処理では、微生物の力を借りて汚れた水をきれいにする「活性汚泥法」という方法がよく使われます。
活性汚泥とは、この水の中にいる微生物たちの集まりのこと。
この微生物たちが、汚れた水の中の汚れを食べてくれることで、水がきれいになるのです。
バルキングってどんな状態?
ところが、この活性汚泥の中にいる微生物が、何らかの原因で異常に増えてしまうことがあります。
すると、汚泥がフワフワと膨らんで、水と分離しにくくなってしまうのです。この状態を「バルキング」と言います。バルキングが起こると、
- きれいになった水の中に汚泥が混じってしまう
- 汚泥が沈殿槽からあふれてしまう
といった問題が起こり、排水処理がうまくいかなくなってしまいます。
バルキングの種類
バルキングには、大きく分けて2つの種類があります。
糸状性バルキング
一つは「糸状性バルキング」と呼ばれるもので、糸状菌という微生物が異常に増えることで起こります。この糸状性バルキングの原因としては、
- 栄養のバランスが悪いこと
- 水の中に酸素が足りないこと
- 水のpH(酸性・アルカリ性の度合い)がおかしいこと
などが挙げられます。
非糸状性バルキング
もう一つは「非糸状性バルキング」と呼ばれるもので、ネバネバした物質を作る微生物が異常に増えることで起こります。非糸状性バルキングの原因としては、
- 汚れが多すぎること
- 微生物に必要な栄養が足りないこと
などが考えられます。
バルキングの対策
バルキングが起こってしまったら、原因に合わせて対策をする必要があります。
糸状性バルキングの対策
糸状性バルキングの場合は、
- 栄養のバランスを整えたり
- 水の中に酸素をしっかり送り込んだり
- 水のpHを適切な状態にしたり
- 薬剤を使って糸状菌を減らしたり
といった対策が考えられます。
非糸状性バルキングの対策
非糸状性バルキングの場合は、
- 汚れを減らすための処理を強化したり
- 微生物に必要な栄養を補給したり
といった対策が有効です。
バルキングの予防
しかし、バルキングは、起こってから対策するよりも、日頃から予防することが大切です。
そのためには、
- 水の汚れ具合や汚泥の状態を毎日チェックしたり
- 水の中に酸素を送り込む装置や、汚泥を沈めるための装置などを定期的に点検したり
- 工場などから、バルキングの原因になるような物質が流れ込まないようにしたり
といった日々の管理が重要になります。
まとめ
バルキングは、排水処理の現場でよくあるトラブルの一つですが、原因をしっかり理解して、適切な対策をすれば、必ず解決できます。
日頃から水の状態をよく観察して、バルキングを予防することが大切です。
もし、どうしたらいいか分からなくなって困ってしまったら、専門業者に相談するのが一番です。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。


