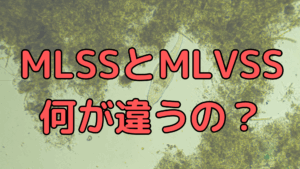N-BOD(窒素性BOD)の理解とBOD測定における注意点:植種と硝化抑制の重要性
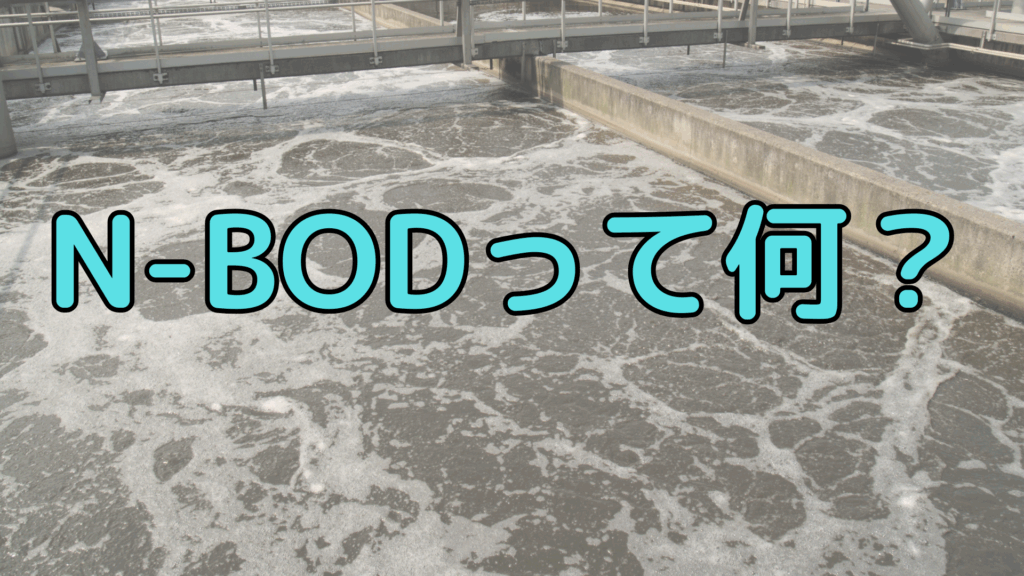
河川や工場排水などの水質を評価する際、最も広く用いられる指標の一つがBOD(生物化学的酸素要求量)です。
BODは、水中の好気性微生物が有機物を分解する際に消費する酸素の量を示し、その値が高いほど水が有機物によって汚れていることを意味します。このBODは水環境保全や排水管理において非常に重要な指標です。
しかし、一言でBODと言っても、その内訳は単純ではありません。微生物が分解するのは有機物(炭素化合物)だけではないからです。
水中の窒素化合物、特にアンモニア態窒素も、特定の条件下では微生物によって酸化され、酸素を消費します。この窒素化合物由来の酸素消費量をN-BOD(窒素性BOD)、硝化抑制剤を加えて、窒素由来の酸素消費を抑えた有機物由来の酸素消費量をC-BOD(炭素性BOD)またはATU-BOD(アリルチオ尿素:ATU)と呼びます。
水処理や正確な水質評価を行う上で、このN-BODの存在を理解し、適切に評価・管理することが不可欠です。本記事では、N-BODの基本原理から、BOD測定時に注意すべき点、特に「植種」の選択や「硝化抑制」の重要性について解説します。
N-BOD(窒素性BOD)とは何か?
N-BODは、主に硝化細菌と呼ばれる微生物の働きによって、水中のアンモニア態窒素 (NH4+) や亜硝酸態窒素 (NO2−) が、最終的に硝酸態窒素 (NO3−) へと酸化される過程(硝化反応)で消費される酸素の量です。
硝化反応は以下の二段階で進行します。
- アンモニア酸化: アンモニア態窒素 (NH4+) → 亜硝酸態窒素 (NO2−) (亜硝酸菌)
- 亜硝酸酸化: 亜硝酸態窒素 (NO2−) → 硝酸態窒素 (NO3−) (硝酸菌)
このプロセス全体で相当量の酸素が消費されるため(NH4−N 1gあたり約4.57gのO2)、N-BODは水域の溶存酸素を低下させる大きな要因となり得ます。
また、窒素化合物は富栄養化の原因物質でもあるため、排水基準で規制されることも多く、水処理プロセスにおける窒素除去(硝化・脱窒)は重要な課題です。
通常のBOD測定における課題:C-BODとN-BODの混在
一般的なBOD測定法(例:5日間培養する BOD5)では、試料水中の微生物(または添加した植種)が活動し、酸素を消費します。
この際、試料中に有機物とアンモニア態窒素が共存し、かつ硝化細菌が存在する環境であれば、C-BODとN-BODの両方の反応が同時に進行する可能性があります。
その結果、測定されるBOD値は、純粋な有機物汚濁を示すC-BODだけでなく、N-BODの影響を含んだ、いわば「合計値」に近いものとなる場合があります。
これは、有機物負荷を正確に把握したい場合や、排水処理プロセスの効率を評価する上で問題となることがあります。
BOD測定における「植種」の役割とその影響
BOD測定を正確に行うためには、試料中に十分な量の有機物分解微生物が存在する必要があります。
しかし、試料によっては微生物が少ないため、外部から微生物源を添加します。これが「植種」または「種汚泥」です。活性汚泥、河川水、土壌抽出液などが用いられます。
ここで重要になるのが、使用する植種の種類や状態がN-BODの発現に大きく影響するという点です。
多くの排水処理場で用いられる活性汚泥には、有機物分解菌だけでなく硝化細菌も含まれています。
そのため、活性汚泥を植種として使用すると、BOD測定中に硝化反応が起こりやすく、N-BODが測定値に含まれやすくなります。植種中の硝化細菌の量や活性度によって、N-BODの影響度は変動します。
N-BODの影響を制御する方法:ATU添加法
では、N-BODの影響を意図的に排除し、有機物汚濁の指標であるC-BODをより正確に測定するにはどうすればよいでしょうか。
最も一般的で確実な方法は、硝化抑制剤 ATU(アリルチオ尿素) を使用することです。
ATUは、硝化反応の最初のステップであるアンモニア酸化酵素の働きを選択的に阻害します。BOD測定を行う際に、試料と植種に規定量のATUを添加することで、硝化反応による酸素消費(N-BOD)を効果的に抑制できます。
これにより、測定されるBOD値は、ほぼC-BODのみを反映したものとなります。
この方法は「ATU添加BOD測定」や「硝化抑制BOD測定」と呼ばれ、JIS K 0102(工場排水試験方法)などでも、N-BODの影響を除去したい場合に用いる方法として採用されています。
有機物負荷を正確に評価したい場合には、この方法が非常に有効です。ただし、試薬コストがかかる点や、測定目的に応じてATU添加の要否を判断する必要がある点には留意が必要です。
適切なBOD測定方法の選択
ATUを添加するかどうかは、BOD測定の目的に応じて選択することが重要です。
- 有機物除去効率の評価など、C-BODを正確に知りたい場合: ATU添加BOD測定を選択します。
- 放流先の水域への総酸素消費影響を知りたい場合: ATUを添加しないBOD測定結果と、別途測定した窒素濃度などを合わせて総合的に評価する必要があります。
水処理におけるN-BOD管理
活性汚泥法などの生物学的排水処理においては、単に有機物(C-BOD)を除去するだけでなく、窒素化合物(N-BODの原因)を除去することも求められます。
これには、曝気槽でアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える「硝化」と、その硝酸態窒素を嫌気条件下で窒素ガスに変えて除去する「脱窒」という二つのプロセスを適切に制御することが重要です。
十分な酸素供給、適切なpH・水温管理、十分な汚泥滞留時間(SRT)の確保などが、安定した窒素除去(N-BOD対策)の鍵となります。
まとめ
BOD測定は水質管理の基本ですが、N-BODの存在や植種の影響など、その解釈には注意が必要です。特に窒素規制が厳しい場合や、高度な排水処理を行う場合には、C-BODとN-BODの両方を意識した管理が不可欠です。
BOD測定の方法選択、結果の解釈、そして水処理プロセスにおけるN-BOD対策や窒素除去には、専門的な知識と経験が求められます。
もし、これらの点に関して課題や疑問をお持ちでしたら、まずは信頼できる水処理の専門業者に相談することをお勧めします。現状の詳細な分析に基づき、的確なアドバイスや解決策を得ることができるでしょう。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。