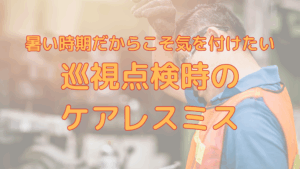水処理施設における夏季の藻類・スライム発生原因と対策の要点
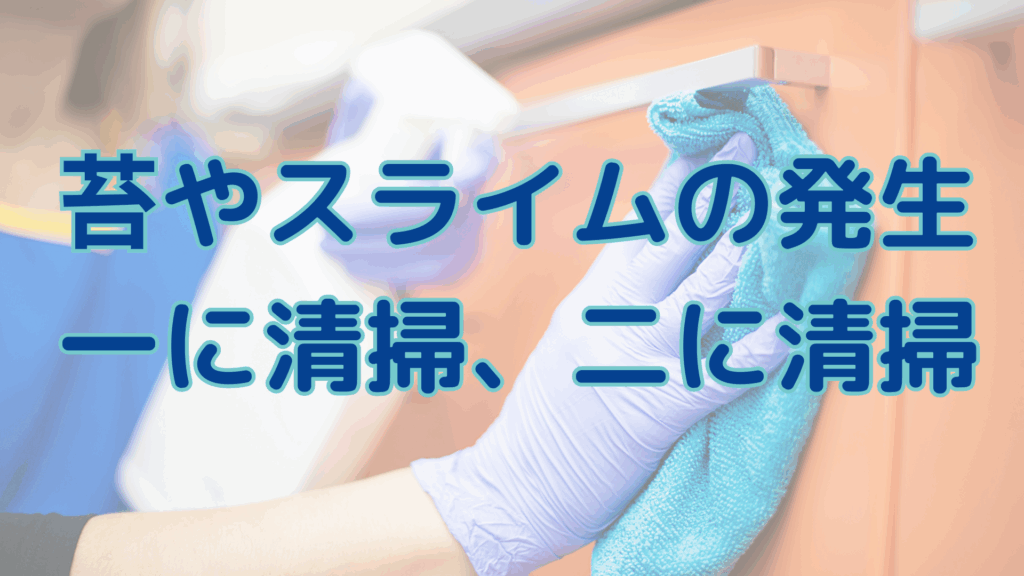
水処理施設の安定稼働において、夏場は特に注意が必要な季節です。気温と水温の上昇に伴い、多くの現場で苔(藻類)やスライム(生物膜)の発生が問題となります。これらは見た目の問題だけでなく、水処理能力の低下や設備の不具合に直結する深刻な課題です。
本記事では、夏季にこれらの微生物がなぜ発生しやすくなるのか、そしてその対策として最も重要となる基本的なアプローチについて解説します。
なぜ夏場に苔やスライムは発生しやすいのか?
苔やスライムが夏場に急増する主な要因は、微生物の繁殖に適した環境が整うためです。具体的には、以下の3つの要素が大きく関係しています。
- 水温の上昇 微生物の多くは、水温が高いほど活動が活発になります。特に20℃~30℃の範囲は、多くの細菌や藻類にとって最適な増殖温度帯です。夏場は冷却塔や調整槽、沈殿槽などの水温がこの範囲に入りやすく、微生物が爆発的に繁殖するリスクが高まります。
- 日照時間の増加と日差しの強さ 苔(藻類)は植物の一種であり、光合成によって増殖します。夏場は日照時間が長く、日差しも強くなるため、屋外に設置された沈殿槽や開放水路など、光が当たる場所では藻類の光合成が活発化し、著しく繁殖します。
- 水中の栄養塩類 水処理の対象となる排水中には、微生物の栄養源となる窒素やリンといった栄養塩類が豊富に含まれています。これらの栄養塩類と、前述の「水温」「光」という条件が揃うことで、富栄養化が加速し、苔やスライムの大量発生を招きます。
苔・スライムが水処理に与える悪影響
発生した苔やスライムを放置すると、水処理プロセス全体に様々な悪影響を及ぼします。
- 配管の閉塞と流量低下: スライムが配管内部に付着・成長することで流路が狭まり、ポンプの揚程ロスや流量の低下を引き起こします。
- 熱交換効率の低下: 冷却塔の充填材や熱交換器の伝熱面にスライムが付着すると、熱の伝達が妨げられ、冷却効率が著しく低下します。
- 処理水質の悪化: 大量に発生した苔やスライムが剥離し、処理水に混入することで、SS(浮遊物質)濃度が上昇します。また、これらの有機物が分解される過程でBODやCODを悪化させる原因ともなります。
- 腐食や悪臭の原因: スライムの内側では、酸素が届きにくい嫌気的な環境が形成されます。そこでは硫酸塩還元菌などの嫌気性菌が繁殖し、設備の腐食や硫化水素のような悪臭を引き起こす可能性があります。
基本にして最も重要な対策「物理的清掃」
これらの問題に対する有効な手段として、殺菌剤やスライムコントロール剤といった薬品の注入が広く行われています。しかし、薬品を投入する「だけ」で根本的な解決に至るケースは稀です。ここで最も重要となるのが、定期的な物理的清掃です。
微生物は「バイオフィルム」と呼ばれる強固な膜を形成して表面に固着します。このバイオフィルムは、外部からの薬品の浸透を防ぐバリアの役割を果たします。そのため、バイオフィルムが厚く成長してしまった状態では、いくら高濃度の薬品を投入しても表層のスライムしか殺菌できず、内部の微生物は生き残ってしまいます。
高圧洗浄機やブラシなどを用いて、槽の壁面や配管、充填材などに付着したスライムや苔を物理的に除去することで、初めて薬剤が効果的に作用する素地が整います。清掃を怠ったまま薬品の使用を続けると、効果が見えないために使用量が増え、結果として薬剤コストの増大につながる悪循環に陥ります。
「対策の基本は清掃にあり」。これは水処理の普遍的な原則です。
薬品注入と清掃の連携
安定した水処理を維持するためには、薬品による「発生の抑制」と、清掃による「根本的な除去」を組み合わせることが不可欠です。
- 春先~梅雨時期: 微生物が活発化し始める前に、一度徹底的な清掃を実施する。
- 夏場: 清掃でクリーンになった状態を維持するために、計画的に薬品を注入する。スライムの発生状況を監視し、必要に応じて部分的な清掃を追加する。
- 秋口: 夏の間に蓄積した汚れをリセットするための清掃を行う。
このように、季節や設備の状況に応じたメンテナンス計画を立て、清掃と薬品処理を連携させることが、トラブルを未然に防ぎ、年間を通じたコストを最適化する鍵となります。
夏場の苔・スライム問題は、多くの水処理現場で直面する課題です。薬品だけに頼るのではなく、基本に立ち返り、物理的な清掃の重要性を見直すことが安定稼働への第一歩です。
もし、これらの対策を行っても状況が改善しない場合や、自社での対応に限界を感じる場合は、水処理の専門業者に相談することをお勧めします。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。