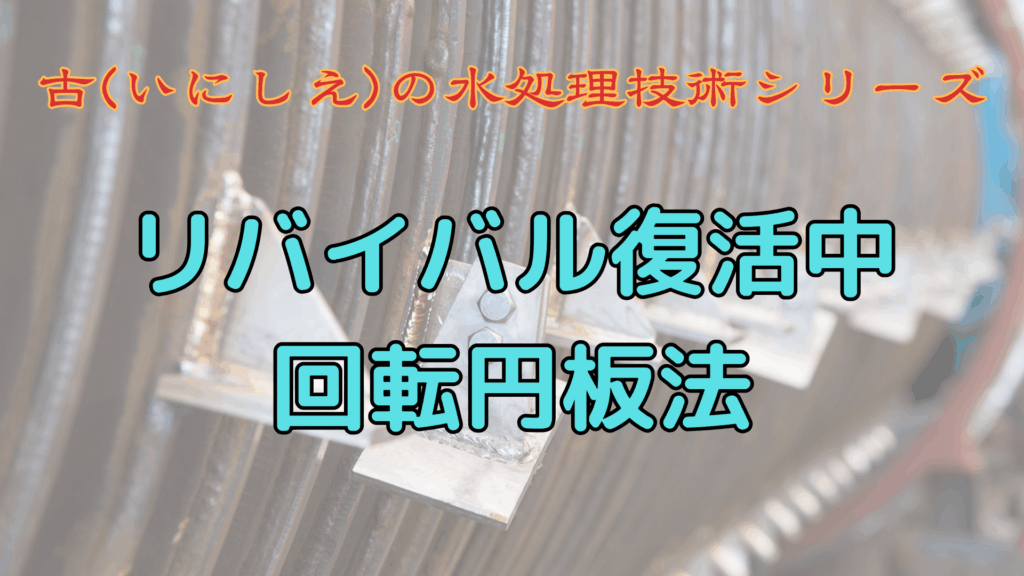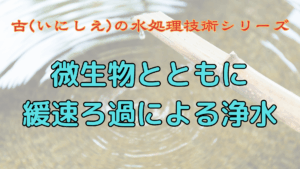【いにしえの水処理技術 第4回】回転円板法 – 省エネ生物膜法の再評価と新たな役割
水処理技術の歴史を紐解く「いにしえの水処理技術」シリーズ。第四回目となる今回は、ユニークな構造で省エネルギーを実現した生物処理法「回転円板法(かいてんえんばんほう)」をご紹介します。一時はあまり普及しなかったこの技術が、現代のニーズに応える形で新たな価値を見出され、再び注目を集めています。
回転円板法とは?
回転円板法は、散水ろ床法などと同じ「生物膜法」の一種です。プラスチックなどで作られた多数の円板(ディスク)を一本の軸に固定し、その円板の下部約40%が排水で満たされた水槽に浸かるように設置します。この軸をゆっくりと回転させることで、排水の浄化を行います。
空気を“呼吸”する浄化の仕組み
回転円板法の最大の特徴は、その浄化メカニズムにあります。
- 汚濁物質の吸着: 円板が回転して排水に浸かると、表面に形成された生物膜(微生物の集合体)が、排水中の有機物などを吸着・分解します。
- 空気中での酸素供給: 次に円板が回転して空気中に出ると、濡れた生物膜の表面に直接空気が触れます。これにより、微生物は活動に必要な酸素を効率的に取り込むことができます。
この「排水に浸かって栄養を摂り、空気に出て呼吸する」というサイクルを繰り返すことで、排水は浄化されていきます。活性汚泥法のようにブロワーで強制的に空気を送り込む(曝気)必要がないため、省エネルギー性能に優れているのが大きな利点です。
かつてのメリットと課題
回転円板法は、その省エネ性以外にも、運転管理が比較的容易で、汚泥発生量も少ないというメリットがありました。しかし、日本で爆発的に普及するには至りませんでした。その背景には、いくつかの課題があったとされています。
- 機械的なメンテナンス: 円板を回転させるための軸やベアリング、駆動装置といった機械部分の維持管理に手間がかかる。
- 生物膜の重量問題: 生物膜が過剰に厚くなると、円板全体の重量が大幅に増加し、回転軸に大きな負荷がかかり、破損の原因となるケースがあった。
- 処理能力の限界: 高度な窒素・りん除去への対応が難しいなど、処理性能の面で、より汎用性の高い活性汚泥法が主流となっていきました。
現代におけるリバイバル – 東芝の事例にみる新たな価値
一度は下火になった回転円板法ですが、近年、その価値が再評価され、新たな形で復活を遂げています。その代表例が、東芝が提案する、オキシデーションディッチ(OD)法の前段処理としての活用です。
オキシデーションディッチ法は、水路型の反応タンクを用いる水処理法で、窒素除去などに優れた性能を発揮します。しかし、処理水量に応じた曝気動力が必要となります。
そこで、OD法の手前にBOD処理装置として、同社の製品であるHabuki™を設置します。
- まず、高濃度の有機物(BOD)を含む排水を、Habukiで処理します。ここで排水中のBODの大部分を除去します。
- BODが大幅に削減された排水を、後段のOD法で処理します。
このように、得意分野の異なる技術を組み合わせることで、プラント全体の消費電力を大幅に削減するというアプローチです。回転円板法を単独の処理方式としてではなく、既存技術の省エネ性能を向上させるための“ブースター”や“プレ処理”として活用する、まさに温故知新のソリューションと言えます。
まとめ:技術は組み合わせで進化する
回転円板法そのものの原理は昔から変わりません。しかし、それをどの工程で、どのような目的で使うか、という「アプリケーション」の発想を変えることで、新たな価値が生まれました。一つの技術だけで全ての課題を解決しようとするのではなく、いにしえの技術が持つ優れた点と現代の技術をインテリジェントに組み合わせることで、より効率的で持続可能な水処理が実現できるのです。この事例は、過去の技術ライブラリにこそ、未来のヒントが眠っていることを教えてくれます。
工場の排水処理や省エネルギー化でお困りの際は、まずはお近くの専門業者にご相談することをお勧めします。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。