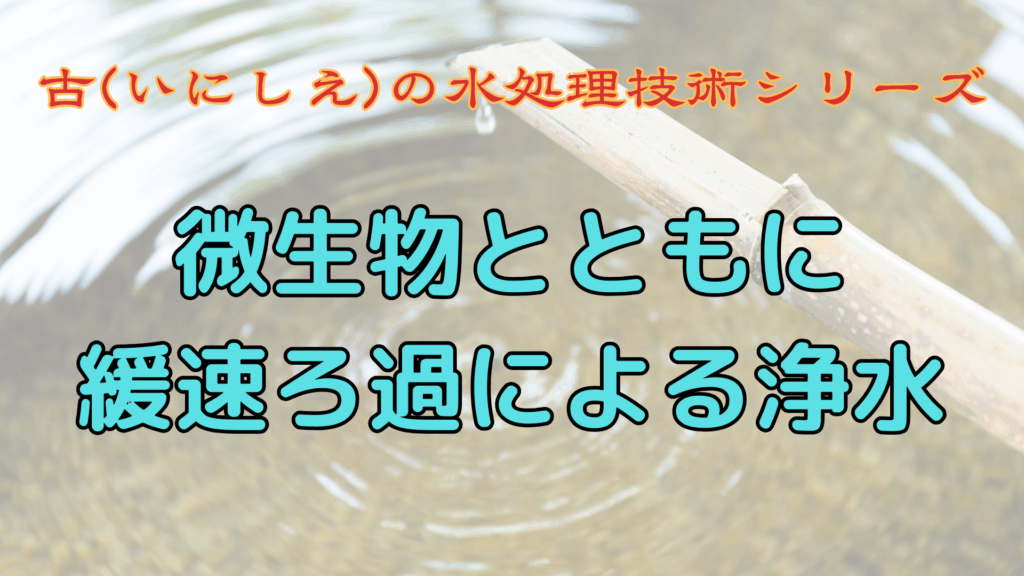【いにしえの水処理技術 第3回】緩速ろ過方式 – 生物が水を磨く浄化の知恵と、その大変さ
水道の蛇口をひねれば当たり前に出てくる安全な水。その安全を支えているのは、多くの場合、薬品などを使った化学的な浄水技術です。しかし、今なお一部の浄水場では、100年以上前から続く、自然の力を巧みに利用した浄水技術が稼働していることをご存知でしょうか。シリーズ第三回目は、生物の力で水を磨き上げる「緩速ろ過方式(かんそくろかほうしき)」をご紹介します。
緩速ろ過方式とは?
緩速ろ過方式は、その名の通り「緩やかな速度で」砂の層に水を通すことで、水をきれいにする浄水方法です。一見すると、ただ砂で水をこしているだけのように思えますが、その心臓部は砂の表面に形成される微生物の層にあります。凝集剤などの薬品をほとんど使わず、自然の浄化作用を最大限に引き出す、非常にサステナブルな技術です。
浄化の主役「生物ろ過膜」
緩速ろ過の浄化メカニズムで最も重要なのが、ろ過池の砂の表面に自然に形成される、厚さ数ミリの粘着性のある膜です。これは「生物ろ過膜」と呼ばれます。
この膜には、藻類、原生動物、バクテリアなど、多種多様な微生物が生息しています。水がこの生物ろ過膜をゆっくりと通過する際に、水中の濁り成分や有機物、病原性のある一般細菌、大腸菌などが微生物に捕食・分解されます。つまり、物理的な「ろ過」だけでなく、生物ろ過膜という小さな生態系が、水を食べてきれいにしてくれるのです。
緩速ろ過のメリット
都市部ではあまり見られなくなった緩速ろ過ですが、優れたメリットを持っています。
- 高い水質と美味しさ クリプトスポリジウムのような薬品に耐性のある病原性微生物の除去能力が高いとされています。また、生物ろ過膜が水中の有機物を効率的に分解・除去してくれるため、浄水後の水に含まれる有機物量が非常に少なくなります。消毒のために使われる塩素は、この有機物と反応して消費されます。したがって、有機物量が少ない水は塩素の消費も少なく、結果として投入する塩素の量を必要最低限に抑えることができます。これにより、水道水特有のカルキ臭が少なくなり、まろやかで美味しい水になると言われています。
- 低ランニングコスト 浄化の主役が生物膜であるため、急速ろ過で必要となる凝集剤が原則不要です。電力も主にポンプ程度しか使わないため、運転にかかる費用を低く抑えることができます。
- 維持管理の容易さ(理論上) 構造がシンプルなため、複雑な機械の操作やメンテナンスは必要ありません。
シンプルだからこそ大変 – 維持管理の難しさ
メリットだけ見ると理想的に思える緩速ろ過ですが、そのシンプルな機構ゆえの、現代の効率性とは相容れない「大変さ」を抱えています。
- 広大な土地が必要 ろ過速度が非常に遅い(1日あたり4~5m程度)ため、同じ量の水を作るのに、薬品を使う急速ろ過方式の何倍もの面積が必要になります。これが、土地の確保が難しい都市部の浄水場から姿を消した最大の理由です。
- 時間のかかる「掻き取り(かきとり)」作業 長期間ろ過を続けると、生物ろ過膜が厚くなりすぎたり、濁りが蓄積したりして、水の通りが悪くなります(目詰まり)。こうなると、薬品で洗浄する急速ろ過とは違い、ろ過池の水を全て抜き、作業員が手作業で、目詰まりした表面の砂を数センチ削り取るという作業が必要になります。これを「掻き取り」と呼び、大変な労力と時間がかかります。
- 生物を「育てる」難しさ 掻き取りの後や、新しい砂を入れた後は、すぐに浄水能力を発揮できるわけではありません。浄化の主役である生物ろ過膜が、再び自然に形成されるまで、数週間から時には数ヶ月待つ必要があります。この間は「捨て水」といって、ろ過した水を浄水として使わずに運転を続け、微生物が育つのを待つのです。このように、緩速ろ過の運転管理は、機械のスイッチを入れるようなものではなく、まるで生き物を育てるような、経験と勘、そして忍耐が求められる職人技なのです。
まとめ:なぜ今も使われ続けるのか
緩速ろ過方式は、効率性や省スペース化が求められる現代の都市部には不向きな面も多いですが、その一方で、低コストで安全かつ良質な水を作り出せるという、代えがたい価値を持っています。自然の摂理に寄り添い、微生物というパートナーと共に水を磨くこの技術は、水処理の原点であり、環境負荷の少ない持続可能な社会を考える上で、私たちに多くの示唆を与えてくれます。
いにしえの技術を知ることは、現代の技術がどのような課題を克服してきたのか、そして私たちがどこへ向かうべきなのかを考える上で、重要な羅針盤となるでしょう。
工場の用水処理や排水処理でお困りの際は、まずはお近くの専門業者にご相談することをお勧めします。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。