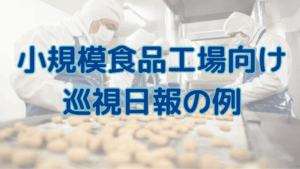【初心者向け】水処理における「含水率」とは?基礎知識と重要性を解説
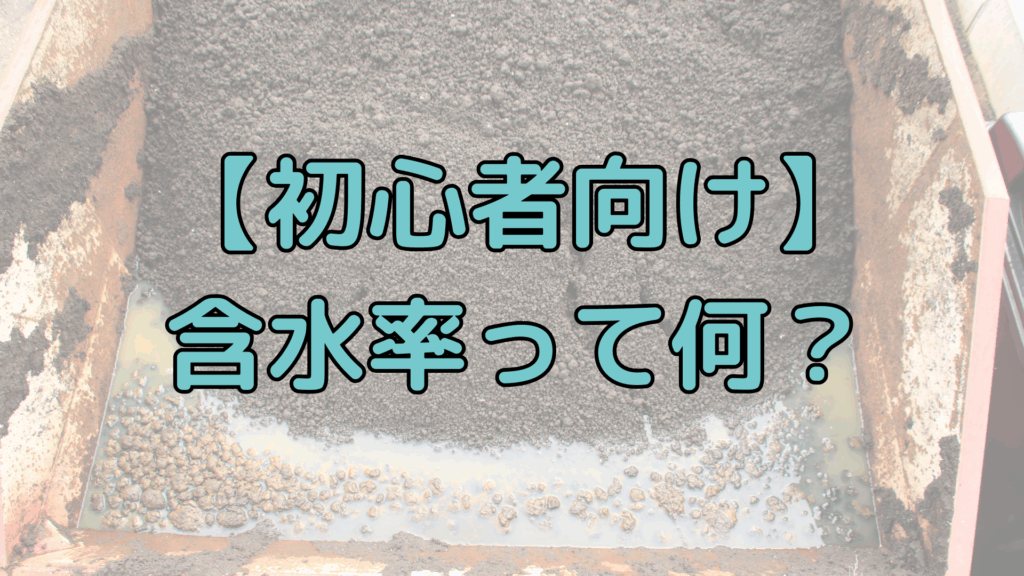
水処理の現場では様々な専門用語が使われます。効率的で安定した運転管理のためには、これらの用語を正しく理解することが不可欠です。
今回はその中でも特に基本的な指標である含水率(がんすいりつ)について、水処理に初めて携わる方向けに、その定義と重要性を解説します。適切な水処理を行う上で欠かせない知識ですので、ぜひご一読ください。
含水率の定義
含水率とは、汚泥や土壌などの物質全体に含まれる水分の重量割合をパーセント(%)で示したものです。
例えば、含水率が90%の汚泥100kgがあった場合、そのうち90kgが水分で、残りの10kgが固形物であることを意味します。 計算式は以下の通りです。
含水率 (%) = (物質中の水分の重量 ÷ 物質全体の重量) × 100
水処理分野、特に汚泥処理においては、この含水率が処理方法の選定や効率を左右する重要なパラメータとなります。
水処理における含水率の重要性
下水処理場や工場の排水処理施設から発生する汚泥(スラッジ)は、通常、含水率が95%以上と非常に高い状態です。これは、汚泥の体積の大部分が水分であることを示しています。 含水率が高いままでは、以下のような問題が生じます。
- 体積の増大: わずかな固形物量に対して大量の水分が含まれるため、汚泥全体の体積が非常に大きくなります。
- 運搬・処分コストの増加: 体積が大きい汚泥を運搬・処分するには、多くの車両や広い処分場が必要となり、コストが増大します。
- 処理効率の低下: 後段の処理(焼却、堆肥化など)を行う際、水分が多いとエネルギー効率が悪くなったり、処理自体が困難になったりします。
このため、水処理プロセスにおいては、汚泥の含水率をいかに効率的に低減させるか(=脱水するか)が重要な課題となります。含水率を1%下げるだけでも、汚泥全体の体積を大幅に削減できる場合があります。
含水率と汚泥処理プロセス
水処理における汚泥処理では、発生した高含水率の汚泥を様々な方法で脱水し、含水率を下げていきます。代表的なプロセスには以下のようなものがあります。
- 濃縮: 比較的簡単な操作で汚泥中の自由水を除去し、含水率を97~98%程度に下げる工程です。
- 脱水: 機械的な力(加圧、遠心力など)を用いてさらに水分を除去し、含水率を70~85%程度まで下げる工程です。脱水機には様々な種類があります。
- 乾燥: 加熱などによりさらに水分を蒸発させ、含水率を大幅に下げる工程です。燃料化や肥料化などの有効利用を目的とする場合に行われます。
これらの処理を通じて含水率を管理し、汚泥の減容化・安定化を図ることが、水処理全体の効率化とコスト削減に繋がります。
含水率の測定方法
含水率の正確な測定は、処理状況を把握し、適切な運転管理を行うために不可欠です。一般的には「乾燥法」と呼ばれる方法で測定されます。
これは、試料を一定の温度(通常105~110℃)で規定時間乾燥させ、乾燥前後の重量差から水分量を算出して含水率を求める方法です。
現場で迅速に測定するための簡易的な水分計もありますが、公定法としては乾燥法が基本となります。
乾燥法での分析が必要な場合は計量証明ができる水質分析会社への依頼が必要です。もし、水質分析会社との取引がない場合、弊社で紹介する事も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
含水率は、水処理、特に汚泥処理の状態を示す基本的ながら非常に重要な指標です。含水率を理解し、適切に管理することが、処理の効率化、コスト削減、そして環境負荷の低減に繋がります。
水処理に関する具体的な処理方法の選定や、現状のプロセスの効率改善についてお悩みの場合は、専門的な知識を持つ業者への相談が不可欠です。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。