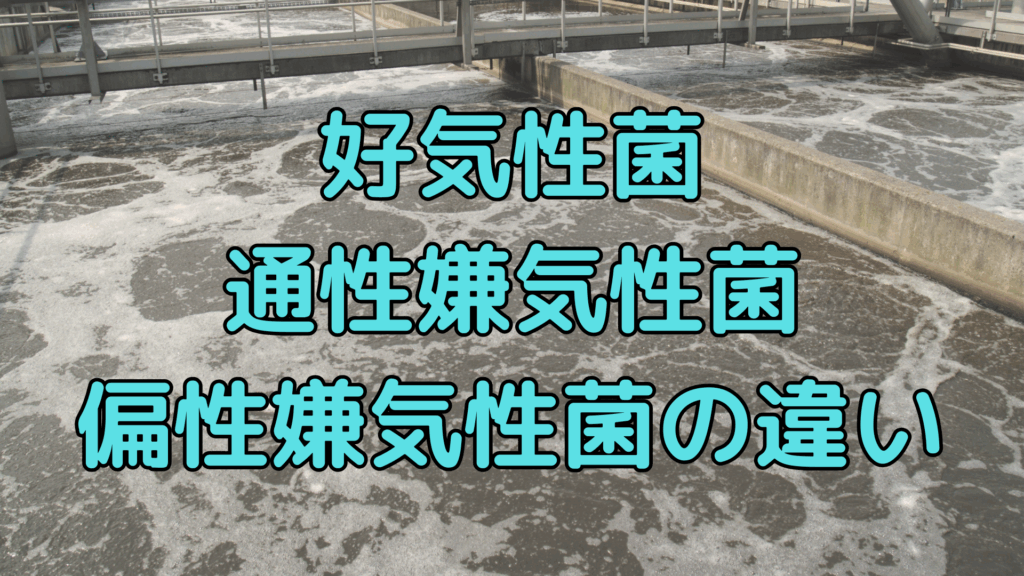水処理における生物学的処理:好気性菌、通性嫌気性菌、偏性嫌気性菌の役割と代表的プロセス
工場の排水処理や下水処理において、「水処理」の根幹をなす技術の一つが「生物処理」です。これは、水中の汚濁物質(有機物など)を微生物の力で分解・除去する方法です。
この生物処理の主役である微生物、特に細菌類は、その「酸素(O2)との関わり方」によって大きく3つに分類されます。それが「好気性菌」「通性嫌気性菌」「偏性嫌気性菌」です。
本記事では、これら3種の菌の違いと、それぞれが水処理プロセスでどのように活用されているかを技術的な観点から解説します。
水処理における微生物の役割
生物処理の目的は、水中の有機物(BODやCODの要因)を、微生物が持つ「代謝」の力を借りて除去することです。微生物は有機物を「エサ」として取り込み、自身のエネルギー源や細胞の構成物質として利用します。
このとき、エサ(有機物)を分解する効率やメカニズムが、酸素の有無によって根本的に異なります。どの菌を優占させて利用するかによって、水処理の設計思想そのものが変わってきます。
1. 好気性菌 (Aerobic Bacteria) とは
酸素が必須な働き者
好気性菌は、その名の通り、酸素(好気)環境でしか増殖・代謝ができない細菌群です。「好気呼吸」と呼ばれる代謝形態を持ち、酸素を最終電子受容体として利用し、有機物を水と二酸化炭素にまで効率よく分解します。
特徴:
- 増殖速度が速い。
- 有機物の分解効率が非常に高い。
- 酸素がなければ活動できない(死滅するものも多い)。
代表的な水処理プロセス:活性汚泥法
好気性菌を利用した水処理の代表格が「活性汚泥法(かっせいおでいほう)」です。 これは、排水(流入水)に「活性汚泥」と呼ばれる微生物の集合体(フロック)を混合し、曝気槽(ばっきそう)と呼ばれるタンクで大量の空気を送り込み(曝気)、好気性菌に有機物を活発に分解させる方法です。
低濃度の有機物から高濃度の有機物まで幅広く対応でき、現在の水処理において最もスタンダードな手法として世界中で採用されています。ただし、常にブロワーなどで空気を送り込むため、動力コスト(電気代)がかかる側面もあります。
2. 偏性嫌気性菌 (Obligate Anaerobic Bacteria) とは
酸素を嫌う専門家
偏性嫌気性菌は、好気性菌とは正反対に、酸素が存在しない環境(嫌気環境)でしか活動できない細菌群です。彼らにとって酸素は有毒であり、曝気されると死滅してしまいます。
特徴:
- 酸素のない環境で有機物を分解する。
- 増殖速度は好気性菌に比べて非常に遅い。
- 高濃度の有機物負荷に強い。
代表的な水処理プロセス:嫌気処理(メタン発酵)
偏性嫌気性菌は、酸素の代わりに硝酸や硫酸、あるいは有機物自体を電子受容体として利用します(嫌気呼吸や発酵)。
代表的なプロセスが「嫌気処理(メタン発酵)」です。 これは、酸素を完全に遮断した嫌気槽内で、偏性嫌気性菌(特にメタン生成菌)の働きにより、有機物を最終的にメタンガス(CH4)、二酸化炭素(CO2)、水に分解する技術です。
特に食品工場や化学工場から出る超高濃度の排水処理に適しています。発生したメタンガスはバイオガスとして回収し、ボイラー燃料や発電に利用できるため、省エネルギー型の水処理として注目されています。
3. 通性嫌気性菌 (Facultative Anaerobic Bacteria) とは
環境適応型のマルチプレイヤー
通性嫌気性菌は、上記2種の中間に位置する、非常に器用な細菌群です。 酸素があれば好気呼吸を行い、酸素がなければ嫌気呼吸や発酵に切り替えることができます。
特徴:
- 環境に応じて代謝を切り替え、生き残ることができる。
- 好気環境下での方が、エネルギー効率は良い。
代表的な水処理プロセス:脱窒素(だっちそ)処理
通性嫌気性菌は、活性汚泥法や嫌気処理のどちらの環境にも存在し、プロセス全体の安定化に寄与しています。
彼らが主役となる代表的なプロセスが、富栄養化の原因となる窒素を除去する「脱窒素処理」です。 水処理における窒素除去は、まず好気環境でアンモニア性窒素(NH4-N)を硝酸性窒素(NO3-N)に変え(硝化)、次に嫌気環境(正確には無酸素環境)で、通性嫌気性菌が硝酸性窒素を窒素ガス(N2)に変えて大気中に放出させます(脱窒)。
この「脱窒」のステップは、通性嫌気性菌が酸素のない環境で、酸素の代わりに硝酸(NO3-N)を呼吸に利用する能力を活用したものです。
まとめ:適材適所の水処理設計
このように、水処理で利用される細菌は、酸素との関係性によって明確に分類されます。
- 好気性菌: 酸素を使い、高速・高効率で分解(例:活性汚泥法)
- 偏性嫌気性菌: 酸素を嫌い、高濃度排水からメタンを生成(例:嫌気処理)
- 通性嫌気性菌: 環境に応じて代謝を切り替え、窒素除去などで活躍
実際の水処理プラントでは、これらの菌が複雑に関わり合いながら機能しています。排水の性質(BOD濃度、窒素・リンの含有量、温度など)に応じて、どの菌の能力を最大限に引き出すかを設計・最適化することが、安定的かつ効率的な水処理の鍵となります。
排水処理の効率が悪い、臭気が発生している、あるいはエネルギーコストを見直したいなど、既存の水処理設備に関するお悩みをお持ちの場合は、専門の業者へ相談することをお勧めします。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。