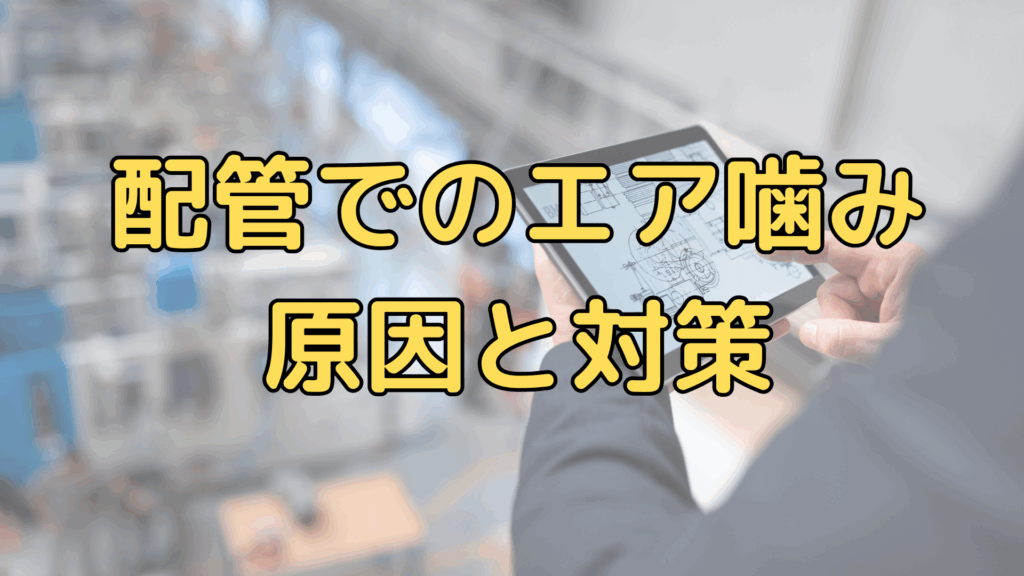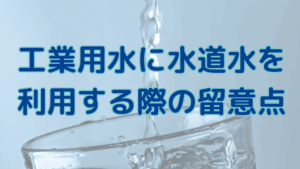水処理における薬品注入時のエア噛み現象:原因と対策
水処理の品質を安定させるためには、薬品を正確な濃度で連続的に注入することが不可欠です。しかし、薬注ポンプの運用において「エア噛み」というトラブルは、多くの現場担当者を悩ませる問題の一つです。本記事では、このエア噛みの原因、特に次亜塩素酸ナトリウムのようなガスを発生しやすい薬品の特性や、試運転時に注意すべき点、そしてその具体的な対策について技術的な観点から解説します。
エア噛みとは?
まず、「エア噛み」とは、薬注ポンプのヘッド(接液部)や配管内に空気が混入・滞留することで、ポンプが正常に薬液を吸引・吐出できなくなる現象を指します。ダイヤフラムポンプやプランジャーポンプといった容積式の薬注ポンプは、液体を扱うことを前提に設計されているため、気体である空気が混入すると、キャビテーションに似た状態となり、定量注入が著しく阻害されたり、完全に停止してしまったりします。
エア噛みの主な原因
エア噛みは様々な要因で発生しますが、主な原因は以下の3つに大別できます。
1. 薬品のガス発生(特に次亜塩素酸ナトリウム)
水処理で多用される次亜塩素酸ナトリウムは、時間経過や温度上昇、紫外線への暴露によって自己分解し、酸素ガス(O₂)を発生させる特性があります。この発生したガスがポンプの吸込側配管やポンプヘッド内に溜まることで、エア噛みを引き起こします。特に、夏場の高温環境下や、薬品タンクの在庫期間が長い場合に顕著に見られる現象です。
2. 配管の施工不備
ポンプの吸込側(サクション側)の配管施工が不適切な場合も、エア噛みの原因となります。
- 長い吸込配管: 吸込側の配管が長すぎると、管内抵抗が増加し、液体が気化しやすくなります(キャビテーション)。
- 逆U字配管: 配管の途中に上向きの凸部(逆U字)があると、その頂点に空気が溜まりやすくなります。
- 接続部の緩み: ホースバンドの締め付け不足や、ネジ接続部のシールテープの不備などから空気を吸い込んでしまうことがあります。
3. 試運転時やタンク液切れ
新しい設備を稼働させる試運転時は、配管内が空の状態でスタートするため、特にエアが噛みやすい状況です。また、運転中に薬品タンクが空になり、ポンプが一度空気を吸い込んでしまうと、薬品を補充してもエアが抜けずに吐出不良が続くことがあります。
エア噛みへの具体的な対策
エア噛みは原因を特定し、それぞれに応じた適切な対策を講じることが重要です。
試運転時の対応:確実なエア抜き作業
試運転時や液切れ後の再開時には、必ず手動でのエア抜き作業が必要です。多くの薬注ポンプには、エア抜き弁やプライミングバルブが備わっています。ポンプを低速で運転させながらこの弁を緩め、ポンプヘッド内の空気を薬液と共に排出します。ブクブクという音と共に空気が抜け、薬液が途切れなく出てくるのを確認してから弁を閉めるのが基本的な手順です。
設備・施工面での対策
恒久的な対策としては、設備の見直しが有効です。
- エア抜き弁(自動・手動)の設置: 配管の最も高い位置や、ポンプの吐出側にエア抜き弁を設置し、定期的にエアを抜けるようにします。
- 配管経路の最適化: ポンプは薬品タンクのできるだけ近くに設置し、吸込配管は最短距離で、かつタンク側からポンプ側へ向かって上り勾配になるように施工します。
- フート弁の活用: 薬品タンクの吸込配管先端にフート弁(逆止弁付きストレーナー)を設置することで、ポンプ停止時に配管内の薬液がタンクに戻るのを防ぎ、エアの混入を低減できます。
ガス発生に対する対策
次亜塩素酸ナトリウムのような薬品に対しては、ガス発生を抑制する管理や、発生したガスに対応できる機器の選定が効果的です。
- 薬品の適切な管理: 薬品タンクは直射日光を避け、風通しの良い涼しい場所に保管します。また、長期在庫を避け、定期的に新しい薬品と入れ替える運用が望ましいです。
- ガス抜き機能付きポンプの採用: 近年では、発生したガスを自動的に排出する機構を備えた「ガス抜き強化型」の薬注ポンプも市販されています。
まとめ:解決が困難な場合は専門家へ
エア噛みは、単純な操作ミスから設備の構造的な問題まで、その原因は多岐にわたります。本記事で紹介した対策を試みても改善しない場合や、複数の要因が複雑に絡み合っているケースも少なくありません。
そのような場合は、無理に自社で解決しようとせず、水処理設備の専門業者へ問い合わせることをお勧めします。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。