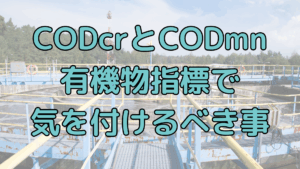水処理の基礎:UV計によるCOD測定の原理と、その「落とし穴」
工場の水処理や環境管理において、水質の汚濁状況を示す指標としてCOD(化学的酸素要求量)は非常に重要です。従来、このCOD測定はJIS法(公定法)に基づき、試薬を用いた手分析や大型の自動測定器で行われるのが一般的でした。
しかし、メンテナンスの容易さやリアルタイム性から、UV(紫外線)を利用したCOD計(UV-COD計)を導入する現場が多くなっています。
手軽にCODの「目安」がわかる便利な計測器ですが、その原理と限界を理解せずに数値を鵜呑みにすると、水処理の判断を誤る「落とし穴」にはまる危険性があります。
本記事では、UV計がなぜCODを測定できるのか、そしてその値を利用する上での注意点を技術的に解説します。
なぜUV(紫外線)でCODが測定できるのか?
水処理の対象となる排水中の汚濁物質の多くは「有機物」です。CODとは、この有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸素量で、有機物が多いほどCOD値は高くなります。
一方、UV(紫外線)測定の原理は「吸光光度法」に基づいています。 多くの有機物(特に二重結合や芳香族環を持つもの)は、特定の波長(主に254nm)の紫外線を吸収する性質を持っています。
つまり、排水中の有機物が多いほど、UVの吸収率(吸光度)も高くなる傾向があります。
この「COD(有機物の量)」と「UV吸光度」の間に一定の相関関係(比例関係)が成り立つことを利用し、UV吸光度を測定してCOD値に「換算」しているのがUV-COD計の原理です。
UV-COD計のメリットと活用場面
UV-COD計の最大のメリットは、「試薬が不要」であることと「リアルタイム測定(連続測定)」が可能な点です。
公定法のように分析に時間や手間がかからず、試薬の補充や廃液処理のコストも発生しません。そのため、排水処理設備の流入原水や処理工程の「傾向監視」として非常に有効です。
リアルタイムで水質の変動を捉えることで、処理薬品の注入量を最適化したり、プラントの異常を早期に検知したりする用途で活躍します。
知りすぎると「危ない」?UV測定の限界
便利なUV-COD計ですが、その値はあくまで「換算値」であり、公定法の値とイコールではありません。この特性を理解していないと、重大な判断ミスにつながります。
1. 相関性が崩れるリスク
UV-COD計は、あらかじめ「自社の排水」におけるUV吸光度と公定法COD値の相関(検量線)を設定して運用します。
しかし、製造品目や使用原料が変わり、排水の水質(含まれる有機物の種類)が変化すると、この相関関係が崩れてしまいます。
例えば、UVを吸収しにくい有機物(アルコールや糖類など)の割合が増えた場合、公定法CODは高いのに、UV-COD計は低い値を示し、「水処理がうまくいっている」と誤解する可能性があります。
2. 妨害物質による誤差
UV(254nm)の光は、有機物以外にも吸収されることがあります。代表的な妨害物質は、
「濁度(SS)」と「一部の無機イオン(硝酸性窒素など)」です。
排水が強く濁っている場合、その濁り成分がUVを乱反射・吸収してしまい、実際の有機物汚濁以上にCOD値が高く(悪く)出てしまうことがあります。
UV計を正しく活用する水処理管理
UV-COD計は、それ単体で絶対的な水質を保証するものではなく、「プロセスの監視モニター」として活用するのが正しい姿です。
その特性を理解し、定期的に公定法(手分析や外部委託分析)との比較を行い、相関がズレていないかを確認(校正)することが不可欠です。
UV計は「いつもと違う」という「変化」を捉えることには非常に優れています。その変化が起きた時に、公定法や他の水質計で「何が起きたのか」を詳細に確認する、という使い分けが、高度な水処理管理の鍵となります。
まとめ
水質管理や排水処理のトラブルでお困りの際は、専門の業者に相談することが解決の早道です。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。