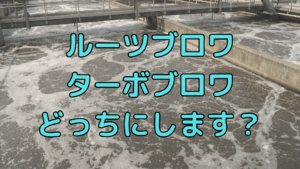水処理における有機物指標の適切な評価:CODcrとCODmnの差異、BOD測定の重要性
水処理計画と有機物指標
工場の排水処理において、水質汚濁の代表的な指標として有機物の量(BODやCOD)が用いられます。これらの指標は、水処理設備の設計や維持管理における根幹となる数値です。しかし、これらの指標、特にCODの測定方法の違いや、BODの数値の解釈を誤ると、処理計画そのものが失敗に終わるリスクがあります。本記事では、水処理の専門家の視点から、CODとBODの適切な評価方法について解説します。
COD測定法:クロム法(CODcr)とマンガン法(CODmn)
COD(化学的酸素要求量)は、水中の被酸化性物質(主として有機物)を酸化するために必要な酸素量を示す指標です。この測定には、使用する酸化剤によって大きく分けて2つの方法が存在します。
CODmn (マンガン法)
過マンガン酸カリウムを酸化剤として使用する方法です。日本では、排水基準などで一般的に用いられているのがこのCODmnです。
CODcr (クロム法)
二クロム酸カリウムを酸化剤として使用する方法です。主に海外(日本以外)で広く採用されています。
酸化力の違いがもたらす「値」の乖離
水処理計画において最も注意すべき点は、CODmnとCODcrの酸化力の違いです。
一般的に、クロム法(CODcr)はマンガン法(CODmn)よりも強力な酸化力を持ちます。そのため、同じ排水を測定した場合、CODcrの方がCODmnよりも高い数値を示す傾向があります。
この差は、分解されにくい有機物をどれだけ酸化できるかに依存します。CODmnでは酸化されなかった有機物が、CODcrでは酸化・検出されるため、数値に乖離が生まれるのです。
海外データ(CODcr)を国内(CODmn)の感覚で扱う危険性
近年、海外のプラントデータを参考に国内の水処理計画を立案するケースも見られます。ここで、海外のデータ(多くはCODcr値)を、日本の基準(CODmn値)と同じ感覚で解釈してしまうと、重大な設計ミスにつながります。
例えば、海外の排水基準が「CODcr 100mg/L」であった場合、これを日本の感覚で「CODmn 100mg/L」と同等とみなしてはいけません。実際には、その排水のCODmn値は100mg/Lよりも大幅に低い(例:50mg/L)可能性があり、逆に日本の「CODmn 100mg/L」の排水をCODcrで測定すると、200mg/L近い値を示すこともあります。
この特性を理解せず、指標の定義(CrかMnか)を確認しないまま計画を進めると、処理設備の容量不足や、逆に過剰設計を招くことになります。
BOD測定の落とし穴:BOD5の解釈
BOD(生物化学的酸素要求量)も、有機物処理、特に生物処理において重要な指標です。一般的にBOD5(5日間培養後のBOD)が用いられます。
しかし、「BOD5が100mg/L」という情報だけでは、その有機物が「処理しやすい」のか「しにくい」のかは判断できません。
BODの分解速度
BOD5は、あくまで5日間の積算値です。その内訳として、最初の1〜2日で急激に酸素が消費される(分解されやすい)のか、5日目ギリギリになってようやく分解が進む(分解されにくい)のかは、BOD5の数値だけでは分かりません。
水処理の計画、特に生物処理の設計においては、単純なCODやBOD5の値から処理能力を推算するのではなく、実際の排水を用いたBODの分解速度(酸素消費速度)を別途測定する必要がある場合も多いのです。
まとめ:適切な水質評価のために
水処理計画を成功させるためには、分析データの背景を正しく理解することが不可欠です。
- COD:その数値はクロム法(CODcr)か、マンガン法(CODmn)か? 日本の基準か、海外の基準か?
- BOD:BOD5の値だけでなく、分解されやすい有機物か、されにくい有機物か?
これらの評価を誤ると、コストに見合った水処理は実現できません。
水処理設備の計画や既存設備の改善でお悩みの際は、まず専門業者へご相談ください。
専門業者が周りにいない時や、第三者の意見を聞きたいときは、工場のセカンドオピニオンであるウォーターデジタル社にぜひお問い合わせください。